
高齢化が進む日本では、「親の介護」が他人事ではなくなっています。
いざというときに慌てないためには、事前の備えと知識が不可欠です。
この記事では、親の介護に必要な費用や公的支援制度、仕事との両立方法についてわかりやすく解説します。
さらに、実際に親の介護を経験した方の事例や、民間サービス、相続・成年後見制度との関連についても詳しくご紹介します。
1. 介護にかかる費用の目安
介護にかかる費用は、在宅か施設か、要介護度やサービス内容によって大きく異なります。
以下は、在宅介護と施設介護での一般的な費用の目安です。
| 介護の形態 | 月額費用の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 在宅介護 | 5万〜15万円 | 介護サービス利用料、生活費、医療費など |
| 施設介護 | 15万〜30万円 | 入居一時金、月額利用料、医療・日常生活費など |
特に施設介護は、入居時に数百万円の一時金が必要になることもあります。
在宅でも、家族の介護負担に加え、バリアフリー化のリフォームや介護用品購入などの出費がかさむことも。
2. 介護保険制度の基本
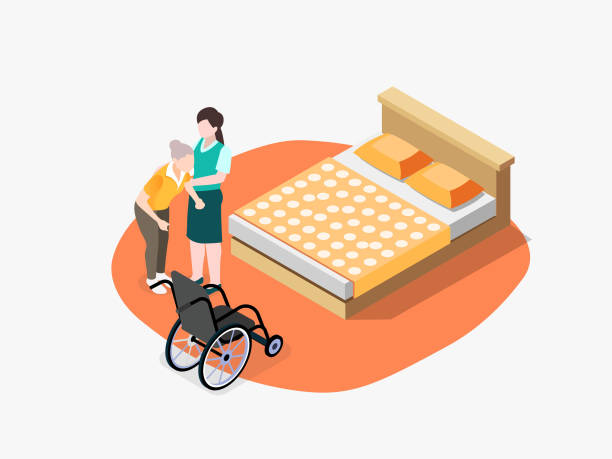
日本では40歳以上になると「介護保険料」を支払います。
介護が必要になったとき、この介護保険を利用することで、自己負担を1〜3割に抑えることができます。
主なサービスの種類:
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所(ショートステイ)
- 特別養護老人ホームなどへの入居支援
要介護認定によって、利用できるサービスの内容や支給限度額が決まります。
3. 詳細な介護保険の申請手順
介護保険を利用するには、以下の手順を踏む必要があります。
- 市区町村の介護保険窓口で「要介護認定」を申請する
- 認定調査員が自宅を訪問し、本人の心身の状態を調査する
- 医師による意見書を基に、介護認定審査会で要介護度が決定される
- 要介護度に応じた「介護サービス計画(ケアプラン)」をケアマネジャーと作成する
- 各種介護サービスの利用を開始
申請から認定までには1ヶ月程度かかることが多いため、早めの準備が肝心です。
4. 民間介護サービスの活用方法
公的な介護保険ではカバーできないニーズに対しては、民間のサービスが選択肢となります。
| サービス名 | 内容 | 費用の目安 |
| 家事代行 | 掃除、洗濯、買い物代行など | 1時間あたり3,000〜5,000円 |
| 訪問介護(自費) | 身体介護や見守りなど(保険外) | 1時間あたり4,000〜6,000円 |
| 見守りサービス | 定期的な電話や訪問、センサー付き家電など | 月額3,000〜8,000円 |
これらのサービスは柔軟に利用できるため、家族の負担軽減に有効です。
特に、遠方に住む子ども世帯が親を支援する場合に役立ちます。
しかし、毎回費用が発生する為に、家計を大きく圧迫していくことが難点です。
継続した利用が出来るようにするには、家計改善も同時に必要となるでしょう。
5. 介護と仕事の両立方法

働きながら親の介護をする「ビジネスケアラー」が増加しています。
会社員であれば、以下の制度を活用できます。
- 介護休業制度:最大93日まで休業可能(分割取得可)
- 介護休暇:1年間に5日(2人以上で10日)の休暇取得が可能
- 短時間勤務制度:労働時間を短縮できる制度
これらの制度は労働基準法や育児・介護休業法によって守られており、会社に申し出れば利用できます。
ただし、企業規模や職種によっては取得しづらい場合もあるため、職場とのコミュニケーションが重要です。
6. ケーススタディ:親の介護を経験した40代女性の声
会社員のAさん(43歳)は、70代の母親が転倒をきっかけに要介護認定を受けることになりました。
最初は何から手をつければよいか分からず、市役所に相談してケアマネジャーを紹介してもらいました。
介護保険を使って、訪問介護(週2回)とデイサービス(週3回)を併用しながら、週2回は自分でも介護を行っています。
実際にかかっている費用は以下の通りです:
- デイサービス利用料(自己負担1割):約12,000円/月
- 訪問介護(1回30分×週2回):約6,000円/月
- バリアフリー化のリフォーム(手すり設置、段差解消など):約25万円(初期費用)
- 介護用品(紙おむつ、消耗品など):約8,000円/月
介護開始から1年で、累計費用は約45万円にのぼっています(うち初期費用25万円)。
Aさんは「最初は不安ばかりでしたが、制度やサービスを知ることで精神的にも負担が減った」と語ります。
また、会社の理解もあり、週に1日はテレワークに切り替えて対応しているそうです。
このように、制度と支援を上手く活用すれば、仕事と介護の両立は可能です。
7. 介護と相続・成年後見制度の関係
介護を進めていく中で、親の財産管理や意思決定をどうするかという問題も出てきます。
そこで知っておきたいのが以下の制度です。
成年後見制度
認知症などで判断能力が低下した場合、家庭裁判所に申し立てることで、代理で財産管理や契約を行う「成年後見人」を選任できます。
家族が後見人になるケースが多く、親の資産を守りながら介護サービスの契約などを進められます。
任意後見制度
親が元気なうちに「この人に後見をお願いする」という契約を結んでおく制度です。
将来の不安を軽減するためにも、早めの検討がおすすめです。
相続との関係
介護を担う家族が一人に偏ると、相続時にトラブルになることも。
「介護したのに何ももらえなかった」といった感情の対立を避けるためにも、遺言書の作成や家族会議を行っておくと安心です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 親の介護は突然始まることが多いと聞きましたが本当ですか?
A. はい。病気や転倒などをきっかけに、ある日突然介護が必要になるケースが多いです。
Q2. ケアマネジャーは誰が選んでくれるの?
A. 市区町村の窓口に相談すれば、地域包括支援センターなどを通じて紹介してもらえます。
Q3. 介護休業を取ると給与はどうなりますか?
A. 雇用保険から一定の給付金(介護休業給付)が支給されますが、収入は通常より減少します。
Q4. 介護にかかる費用を節約する方法はありますか?
A. 介護保険の活用が第一ですが、福祉用具のレンタルや地域の助成制度を活用することで節約が可能です。
まとめ
親の介護は、突然やってくる人生の転機です。
精神的・経済的な負担を減らすためには、介護保険制度や各種支援サービスを正しく理解し、事前に準備をしておくことが何より大切です。
また、仕事との両立や家族の協力体制、相続・財産管理など、幅広い視点からの備えも欠かせません。
今回ご紹介した制度や手順、実例などを参考に、いざというときに後悔しないよう、今からできる準備を始めましょう。


