
仕事ができなくなったとき、生活費をどうするか考えたことはありますか?
病気やケガで長期間働けなくなった場合、収入が途絶えるリスクがあります。 そんなときに役立つのが「就業不能保険」です。
本記事では、就業不能保険の仕組みや必要性、選び方について初心者にも分かりやすく解説します。
1. 就業不能保険とは?
就業不能保険とは、病気やケガで働けなくなった際に、一定期間の給付金を受け取れる保険です。
特に長期療養が必要になった場合、公的保障だけでは生活費をカバーしきれないことが多く、補填する役割を果たします。
この保険は、主に就業不能状態になった際の生活費を補うことを目的としています。
たとえば、サラリーマンであれば「傷病手当金」などの公的補償がありますが、それだけでは十分ではない場合が多く、 就業不能保険に加入することで、より安心して生活を維持できます。
2. 公的保障だけで足りる?
会社員であれば「傷病手当金」が支給されますが、最大1年6か月間のみです。
長期間にわたる療養が必要になると、収入減少が避けられません。
更に、自営業者やフリーランスは、収入が完全にストップするため、 就業不能保険が生活の支えとなることが多いです。
しかし、預貯金+資産運用で十分な資産を準備することで、就業不能保険の必要性は大きく下がります。
3. 会社員・自営業の収入リスク比較
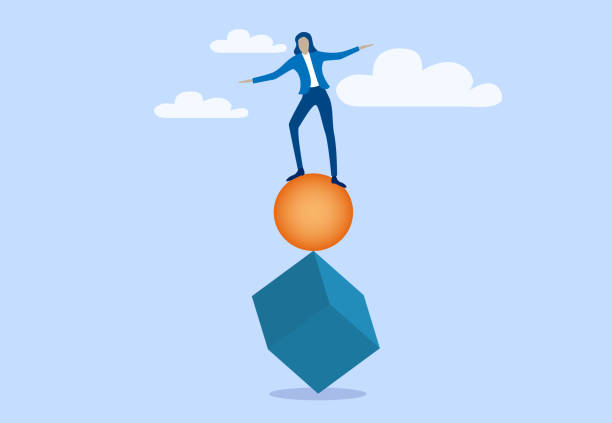
公的保障の少ない自営業者やフリーランスほど、就業不能保険の必要性は高いでしょう。
一方で、会社員であれば傷病手当金で一定期間は収入が継続するため、就業不能保険の必要性は低いと考えられます。
| 項目 | 会社員 | 自営業 |
|---|---|---|
| 傷病手当金 | あり(最長1年6か月) | なし |
| 失業手当 | あり | なし |
| 就業不能保険の必要性 | 低 | 中 |
4. 就業不能保険のメリット
1. 収入が途絶えたときの生活費を補填できる
病気やケガで働けなくなった場合、住宅ローンや生活費の支払いが大きな負担となります。
就業不能保険に加入していれば、一定額の給付金を受け取ることで生活を維持することが可能です。
2. 公的保障と併用できる
会社員の場合、傷病手当金と合わせて利用することで、生活費の安定を図れます。
公的保障だけでは不足しがちな部分を補えるため、安心感が増します。
3. 保険料控除の対象になることも
一定の条件を満たせば、生命保険料控除の対象となることがあります。
税金の負担軽減にもつながるため、長期的に見てお得です。
5. 就業不能保険のデメリット
就業不能保険には多くのメリットがありますが、一方で注意すべきデメリットもあります。
加入を検討する際には、以下の点を十分に理解し、自分に合った選択をすることが大切です。
1. 保険料が比較的高い
就業不能保険は、生命保険や医療保険に比べて保険料が高くなる傾向があります。
特に長期間の保障を求める場合や、給付金額を高めに設定すると、保険料の負担が大きくなることがあります。
加入する際には、家計の支出とのバランスを考え、無理のない範囲で選ぶことが重要です。
2. 免責期間がある
ほとんどの就業不能保険には、給付が開始されるまでの「免責期間」が設けられています。
たとえば、60日や90日など、一定の期間が経過しないと給付金を受け取ることができません。
短期間の休業であればカバーされないため、すぐに保障を受けたい場合には注意が必要です。
3. 一部の病気やケガが対象外になることも
就業不能保険では、保険会社ごとに対象となる病気やケガが異なります。
精神疾患や軽度の病気による就業不能は給付対象外となることが多く、 事前に契約内容をよく確認することが重要です。
また、持病がある場合は、加入できないこともあるため、申し込み時の審査にも注意が必要です。
6. 就業不能保険の選び方
1. 保障期間の長さを確認
保障期間は、就業不能状態が続いた場合にどれだけの期間給付を受けられるかを決める重要な要素です。
短期間の補償では生活を維持できない可能性があるため、できるだけ長い期間を選ぶのが理想的です。
特に、長期療養が必要な病気や障害を考慮すると、最低でも3年以上の保障が望ましいでしょう。
契約する際には、満期時にどのような対応がされるのかも確認し、必要に応じて更新可能なプランを選ぶことが重要です。
2. 給付金額の目安
給付金額は、月々の生活費をどの程度補填できるかを左右するため、慎重に設定する必要があります。
一般的には、手取り収入の50~70%程度を目安に設定するのが適切とされています。
例えば、月収30万円の会社員であれば、15万円~21万円程度の給付金を受け取れるようにすることで、生活の質を大きく落とすことなく療養が可能になります。
また、家族構成や住宅ローンの有無によっても必要な給付金額は変わるため、自身の生活費に基づいて適切な額を選ぶようにしましょう。
3. 免責期間の有無
免責期間とは、保険の給付が開始されるまでの待機期間を指します。
通常、60日~180日程度の免責期間が設定されています。
免責期間が短いほど早く給付を受けることができますが、その分保険料が高くなる傾向があります。
たとえば、短期間での給付が必要な人は免責期間が短いプランを、少しの貯蓄でしばらく生活できる人は保険料を抑えるために長めの免責期間を選ぶのが良いでしょう。
契約する際には、どの病気やケガが免責対象となるのかも確認することが大切です。
7. よくある質問(Q&A)
Q1. 就業不能保険はどのくらいの保険料がかかる?
A. 年齢や保障内容によりますが、30代会社員で月額3,000円~5,000円程度が目安です。 保障内容や給付金額によって異なるため、複数の保険商品を比較することが大切です。
Q2. どの保険会社が良い?
A. 大手生命保険会社やネット保険など複数あります。 比較サイトで自分に合うプランを見つけましょう。
Q3. どんな病気・ケガが対象になる?
A. 多くの場合、ガン・脳卒中・心筋梗塞などの長期療養が必要な病気が対象になります。 ただし、商品によって異なるため確認が必要です。
8. まとめ
就業不能保険は、病気やケガで長期間働けなくなった際に、家計を守るための保険です。
公的保障だけでは不十分な部分に対して、特に自営業者やフリーランスの方であれば、検討する余地はあると言えます。
しかし、保険料は安いとは言えない為、預貯金+資産運用で対策する方が好ましいでしょう。
自分のライフスタイルに合わせた適切なプランを選び、将来のリスクに備えましょう。



